第9回―商人 松延四郎兵衛


当館のある八女福島地区は、江戸時代からの白壁の町並みが残る「伝統的建造物群保存地区」です。この歴史ある地区の守り神として、そして280年以上続く「燈籠人形芝居」の舞台にもなっている「福島八幡宮」。今から364年前の1661(寛文元)年、「福島八幡宮」の建立に最も尽力したとされるある商人がいました。それが福島商人を代表する松延四郎兵衛です。
今回は「福島八幡宮」を語る上で重要な人物の一人、松延四郎兵衛について紹介します。
『松延四郎兵衛の人生』 ■福島八幡宮に至るまでの人生17世紀ごろの福島を代表する商人として活躍した松延四郎兵衛ですが、もとの住居は筑後国内の柳河領(現柳川市)にありました。1626(寛永3)年に松延家に生まれ、父の代に柳河領から高塚村(現八女市大字高塚)に移住します。松延家は、その祖先に戦国時代から安土桃山時代に主に地区全国で活躍した高橋紹運(1548-1586)という武将に仕えた武士を輩出し、武家としての名声を高めていました。高橋紹運の子で筑後柳河3代藩主、立花宗茂(1567-1643)は、あの豊臣秀吉から「東の本田忠勝、西の立花宗茂」と高く評価されるほどの実力者であり、松延家には先見の明があったのかもしれません。また松延家には、現在も続いている「燈籠人形芝居」の成立に大きく関わった「松延甚左衛門(1733-1796)」もおり、筑後に与えた影響力は計り知れないものになっています。そんな松延四郎兵衛ですが、1651(慶安4)年当時25歳の頃、商人になるために福島町へ引っ越してきました。
ここで商人としての才能を遺憾なく発揮し、福島町に越して3年目には蔵を建てるなど、商人としての立ち位置を確立することになります。その後福島町の首長である庄屋に任命(年代不詳)され、町の代表者としての地位も得ることになりました。
■福島八幡宮建立の経緯
1661(寛文元)年に仮社殿でまつられた八幡神でしたが、1671(寛文11)年に松延四郎兵衛とようやく結びつくことになります。当時45歳の松延四郎兵衛は八幡宮正社殿の寄進を発願します。松延四郎兵衛は31歳と41歳の時に伊勢参宮をすませており、その信仰心の厚さから正社殿建立に至ったといわれています。
松延家の家系書「後証修々覚」には八幡宮建立について、「他に計らず」と記しており、八幡宮の寄進を自力で行っていたことが確認されています。当時松延四郎兵衛は金融業も営んでいたため財力があったと考えられます。
1672(寛文12)年8月に神殿が、1681(天和元)年には拝殿が完成したのち、当時55歳の松延四郎兵衛は「後証修々覚」に「此後は神主へ」と記述があるように、建物に関わる一切を八幡宮側に寄附しました。1690(元禄3)年64歳だった松延四郎兵衛は、先祖の大法要を営み、73歳で出家し、「寿安」に改名します。以後は念仏三昧の日々を過ごし、1706(宝永3)年正月5日(現2月19日)に80歳で亡くなりました。

松延四郎兵衛は生前、「親疎貧福を分かたず」とし、当時の城下町民で60歳以上の老人をもてなしたほか、西古松町の無量寿院に仏像を、東矢原町の正福寺に多額の調度品を寄進しました。福島八幡宮建立以外にも町民のために働いた松延四郎兵衛は、福島町を代表する商人だったといえるでしょう。
次回は、「燈籠人形芝居」に動きをもたらした浄瑠璃作者、松延甚左衛門についてご紹介します。


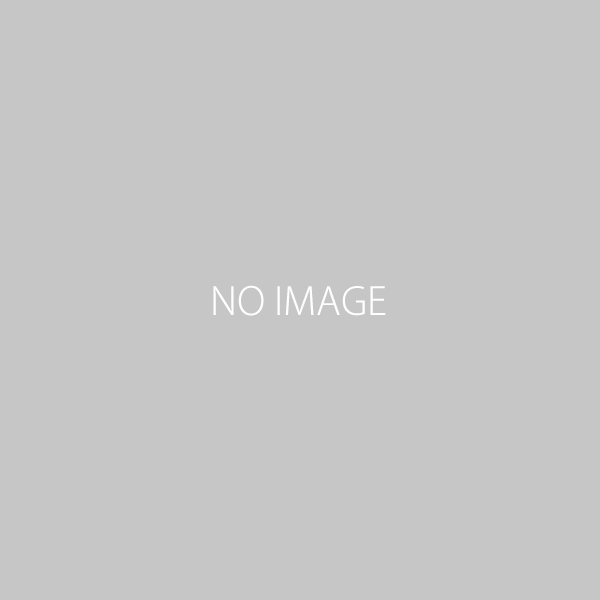
-pdf.jpg)










