第2回燈籠人形 ― 280年以上続く不思議な「からくり」の世界へ


当館のある八女福島地区は、江戸時代からの白壁の町並みが残る「伝統的建造物群保存地区」です。そんな歴史ある八女福島にしかない「燈籠人形芝居」が、今年も秋の夜に命を吹き込みます。
およそ280年続く伝統行事の歴史を、3回に分けてご紹介していきます。
前回は第1回ということで、280年以上も続いている燈籠人形の魅力や課題について語ってきました。
今回は、前回予告していたように燈籠人形の起源やなぜ「燈籠」が選ばれたのか、人形芝居以前の「燈籠」と「人形」との関係性、その不思議な出会いと背景といった「からくり」を紐解いていきます。
『燈籠人形がたどってきたその長い道のり』 ■「からくり」の歴史的背景 〇江戸~明治時代燈籠人形が始まったのは江戸時代で1760年ごろ(宝暦年間)に、福島八幡宮建立100年を祝って、氏子が燈籠を寄進したことが由来といわれていました。当時の秋の放生会では、氏子はその時期になると、家の軒下に神灯を飾る習慣がありました。しかし起源はさらにさかのぼり、1744(延享元)年に熊本県山鹿市の大宮神社から燈籠を放生会に奉納したことに始まります。
1844(天保15)年の「福島燈籠人形の由来」という文書に、「町々軒別御紙燈籠我家我家にとぼすが初り。其後山鹿の燈籠もらつて社内に捧る。是が燈籠と名附る初り。」という記述がみられます。「山鹿からの移入品である紙燈籠は、当初家々に点していたが後々に神殿に奉納する」という内容のものです。
木製の飾り人形
同八幡宮の「放生会記」という一枚刷りには、「古記によれば燈籠人形は1761(宝暦11)年の燈籠奉納に始まる。当時は至って簡素な設備をなし、燈火を点じ飾り人形を陳列奉納したものなるが、次第に改良されて釣糸にて活動せしめ、工夫に工夫を重ね、云々」と書かれています。「燈火を点じ飾り人形を陳列奉納」という点は、人形と燈籠は別物だったことを意味しています。つまり、1761(宝暦11)年時点では、飾り人形が中心であり、燈籠の光によって照らし出される飾り人形を陳列し奉納していたと考えられ、「燈籠が照らし出す人形」を意味しているようです。
からくり人形が登場するのは、11年後の1772(安永元)年。「人形浄瑠璃」の技術と融合し、「燈籠の光によって照らし出される飾り人形の陳列奉納」であった「木製の人形」が「人が操作して動くからくり人形」へと変わり、現在の姿に至ります。以後、燈籠は動く人形を照らす「照明役」に転じました。
1779(安永8)年には久留米櫛原町五穀神社の祭りに、動く「燈籠人形」の初興行の記録が残されており、庶民の秘芸として五穀豊穣、家内安全を願い奉納されました。
しかしながら1842(天保13)年に久留米藩の倹約規制が八女地方にも出され、人形奉納は明治初期まで途絶えます。1845(弘化2)年には久留米藩の大倹令(倹約規制)により上演自体が禁止されますが、1871(明治4)年に復活します。
〇昭和~現在第二次世界大戦の影響で中断されるも、1948(昭和23)年に再開され、1952(昭和27)年には無形文化財として福岡県の指定を受け、1977(昭和52)年には「民俗芸能 渡来芸・舞台芸」の種別で、国の重要無形民俗文化財にも指定されます。

新型コロナウイルスの影響により2020(令和2)年から2021(令和3)年にみたび公演中止に追い込まれましたが、2022(令和4)年から上演が再開され、秋分の日をはさむ3日間に福島八幡宮境内で開催される放生会の奉納行事として現在も上演されています。
■「人形」と「燈籠」の関係性八女福島に伝わる「燈籠人形芝居」は、自然災害や流行病の忌避や身代わりとして作られた「人形(ヒトガタ)」、熊本県山鹿市の大宮神社に奉納された「燈籠」、大阪で隆盛を極めた「人形浄瑠璃」が融合し、筑後上妻郡福島町(現在の八女市)に成立したといわれています。
この章では「燈籠人形」の源流である「人形」と「燈籠」の背景に迫ります。
✔「人形(ヒトガタ)」ここではなぜ人形が関係しているのかをご紹介します。
乳児や幼児の生存率が低かった古代に「病・厄災・けがれの身代わり」のために紙製の「ヒト型人形」が作られるようになります。この由来には、中国から伝わった五節句の一つに「上巳の節句」と呼ばれるものがあり、3月上旬の巳の日に、草や藁で作った「人形(ヒトガタ)」で自分の体を撫でて汚れを移し、それを川に流すことで厄払いや邪気払いを行う風習ではないかと、まことしやかにささやかれています。この「ヒト型人形」は「神霊が降臨しその意志を伝えるための憑依体」「神がよりつく」ものとして、古来より宗教的・呪術的な場面で使用され、8世紀末から12世紀では「人形回し・傀儡回し・木偶回し」と呼ばれる興業師による「人形劇」が社寺近郊で興行されるようになり、人形劇が神社への奉納行事として定着するきっかけとなりました。以降、人形の制作技術が各地に根付くようになります。
✔「燈籠」熊本県山鹿市の大宮神社への「燈籠」の奉納の起源は3説あるといわれていますが、ここでは最も有力な説のみご紹介します。
〇九州を巡幸中の第12代景行天皇(在位;71~130年頃、ヤマトタケルの父)一行が、山鹿の菊池川で濃霧に遭遇した際、里人が一行を松明で山鹿大宮神社まで導いたことを記念して、現社地にある杉山に仮御所(行宮)が設営されました。その後、行宮の跡地に天皇を祀る大宮神社が創建され、はじめは松明が献上されていましたが、いつしか燈籠に変わったと伝えられています。
現存記録からも室町時代にはすでに祭礼用の燈籠が大宮神社に奉納されたことが確認されています。なおこの当時、感染症の大流行や異常気象から、病気平癒や安寧な世を願う行事としての「大宮神社への燈籠の奉納」だったのではないかともいわれています。1592(文禄元)年「文禄・慶長の役」の際、高麗から来朝した春慶・道慶が伝えた「和紙漉き技術」が伝えられ、「燈籠」と「和紙」の技術が融合した「和紙製燈籠」が誕生し、それ以降和紙製が奉納され、慣例化されます。
■まとめ古代からけがれの身代わりとして存在してきた「人形」の制作技術と、大宮神社から奉納された「燈籠」という二つの因子によってここ八女福島に「燈籠人形」のもととなる、「燈籠の機能を備えた人形」が誕生しました。つまりは単なる照明器具に過ぎなかったのです。メインはあくまで人形であり、「燈籠が照らし出す人形」という意味合いが強かったようです。「燈籠人形」という名前においても、当初は四字熟語のように並列的な「燈籠・人形」だったのではないかともいわれています。
■次回予告;動き始める人形
今回はまだ人形は動き出しませんでしたが、次回は「人形浄瑠璃」との関係性や人形が動き、現在のように芝居として公演されるようになったいきさつや経緯についてご紹介していきます。
〇参考文献 ・八女福島の燈籠人形保存会(2009)『八女福島の燈籠人形 復元・修理事業報告』

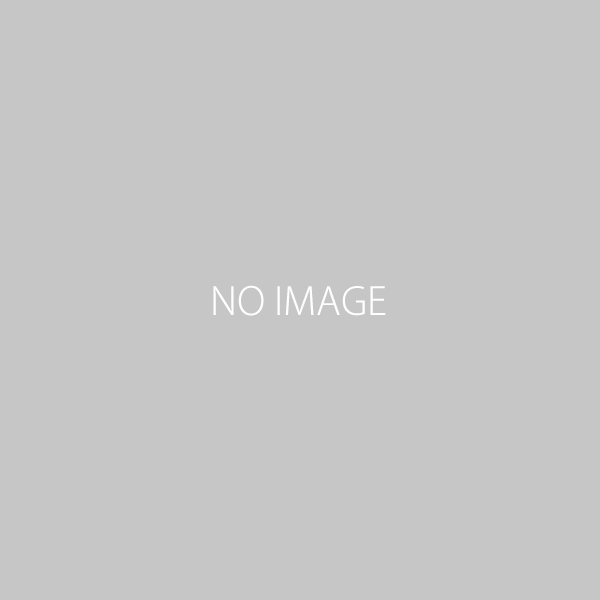
-pdf.jpg)











