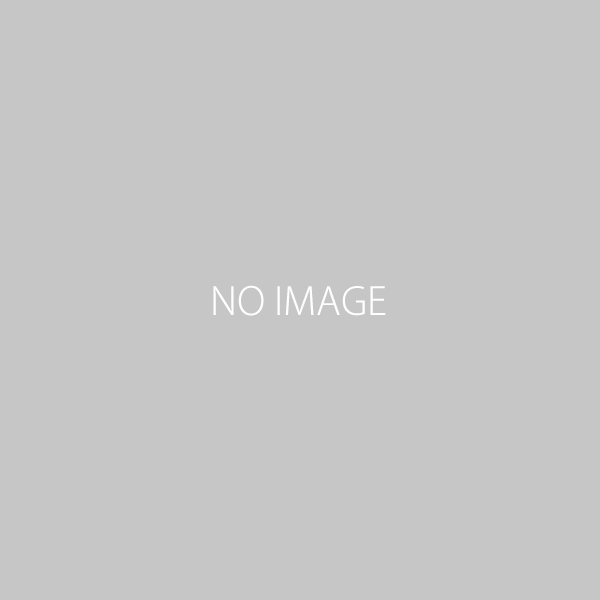第8回-東洋のバルビゾンと呼んだ画家


当館のある八女福島地区は、江戸時代からの白壁の町並みが残る「伝統的建造物群保存地区」です。昔ながらの風景や豊かな自然に囲まれた八女市と、フランス留学時に過ごしたバルビゾン村の風景を重ね、八女市を「東洋のバルビゾン」と呼んだ久留米市出身のある画家がいました。それが八女市に自宅とアトリエを構えた坂本繁二郎です。
今回は「東洋のバルビゾン」と呼んだ洋画家、坂本繁二郎が歩んできた人生についてご紹介します。
『世界的な洋画家、坂本繁二郎』 ■八女に至るまでの人生八女の風土をこよなく愛し、八女市で半生を過ごした坂本繁二郎ですが、生まれは久留米市京町でした。1882(明治15)年に坂本家の次男として出生し、20歳で上京するまで久留米市で暮らしていました。1892(明治25)年当時10歳だった坂本繁二郎は、地元久留米在住の画家、森三美(1872-1913)に従事して絵を学び、その腕前から「神童」と評価される時期もあったそうです。また、同級生には、若くして日本美術史上に残る作品を次々と残した洋画家、青木繁(1882-1911)がおり、よきライバルとして絵の勉強に励んでいました。1902(明治35)年、20歳の時にともに上京し、小山正太郎(1857-1916)が1887(明治20)年に開設した画塾、不同舎に入門します。その後は1907(明治40)年に東京で開催された第1回文部省美術展覧会(現日本美術展覧会)にて『北茂安村の一部』が入選を果たし、第4回では『張り物』が褒状を、第5回では『海岸』が3等賞を受賞します。1912(大正元)年には、1頭の牛が横を向いて立つ光景を硬筆で描いた『うすれ日』が夏目漱石から非常に高い評価を得たことで画家としてのキャリアをスタートさせました。
1910(明治43)年には結婚し、東京に新居を構え、制作を続けます。1921(大正10)年当時39歳だった坂本繁二郎は、さらに絵を学ぶために妻と妻子を地元久留米に残し、単身でフランスへ。制作期間中のほとんどの時間をフランス中北部の都市フォンテンブローの近郊にあるバルビゾン村を過ごし、バルビゾン村の明るい光や風のとりこになっていました。
1924(大正13)年当時42歳の坂本繁二郎は帰国後、地元久留米に戻り、フランスで身に付けた手法で地元の風景を描いた油彩画『放水路の雲』など、数多くの作品の制作に取り掛かりました。
■八女での半生
帰国後坂本繁二郎は約7年間久留米で過ごしたのち、1931(昭和6)年に青木繁とも友人であった梅野満雄の勧めで八女市を訪れます。そこで目にした自然に囲まれた八女市がフランス留学時に過ごしたバルビゾン村の風景と重なり、「東洋のバルビゾン」と呼ぶほどに魅了されたそうです。1948(昭和23)年には本籍を八女市稲富に移し、自宅とアトリエを構え、生涯を八女市で過ごすことになります。
1954(昭和29)年には『水より上がる馬』が第5回毎日美術賞(現毎日芸術賞)で受賞され、八女市の名誉市民となり、1956(昭和31)年には文化勲章を受章します。その後も、成人の日や市政10周年を祝い描いた作品を八女市に寄贈するなど、1969(昭和44)年87歳で没するまで精力的に活動を続けていました。

現在は坂本繁二郎が過ごしたアトリエは残っておらず、旧居のみその内部が観覧可能です。観覧希望者は八女市への届け出が必要となっていますので、市のHP(坂本繁二郎旧居を観覧/八女市ホームページ)でご確認ください。また、八女市立図書館八女本館内2階には坂本繁二郎の絵画や版画、遺品等を展示している資料室がございますので、ぜひ立ち寄ってみてください。
当館から旧居まで徒歩約12分、図書館までは徒歩約5分となっています。
坂本繁二郎旧居;八女市稲富513番地10
八女市立図書館八女本館;八女市本町536番地3
平日:午前10時から午後8時まで
土日・祝:午前10時から午後6時まで
■第50回帰居祭
坂本繁二郎の遺徳をしのぶ式典「帰居祭」が、八女公園内坂本繁二郎画伯寿像前で11月3日(月・祝日)に午前10時から開催されます。「帰居」は、画伯の雅号にちなむもので、八女文化連盟会員による献茶・献花・献吟・献曲をはじめ、小・中・高校生の作文朗読などがあります。当館から八女公園まで徒歩約5分圏内ですのでぜひご参加ください
■次回予告次回は、福島八幡宮建立に一役買った「松延四郎兵衛」についてご紹介します。