第11回― 旧八女郡から八女市への道
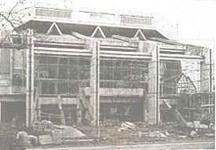
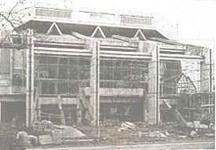
当館のある八女福島地区は、江戸時代からの白壁の町並みが残る「伝統的建造物群保存地区」です。今から438年前に築城された福島城を中心に広がったこの地区は、時代の移り変わりと共に再編され、現在の八女市へと発展してきました。しかし八女市に至るまでに福島町を含む旧八女郡は数奇な運命をたどることになります。
今回は旧八女郡から八女市へと地名が移り変わったその歴史についてご紹介します。
『八女郡から福島市、そして八女市へ』 ■旧八女郡としての歴史現在八女市として70年以上が経過していますが、八女という名前が名付けられたのは1896(明治29)年のことでした。それ以前は、第4回でのご紹介の通り、筑後国福島町として存立していました。しかし1871(明治4)年に行われた廃藩置県により、筑後国は三潴県へとその名を変え、1876(明治9)年には福岡県へと名称を変更されました。1879(明治12)年施行の郡区町村編制法により、行政区画としての上妻郡が設置され、福島町に上妻下妻郡役所が設置されます。上妻郡域としては、現在の星野村を除く八女市の大部分、筑後市の一部、久留米市荒木町周辺、広川町全域が、下妻郡域は現在の筑後市の一部とみやま市の一部がそれに当たります。1889(明治22)年には町村制が施行され、当時の福島町、福島村、稲富村が合併され、今の福島地区となっています。
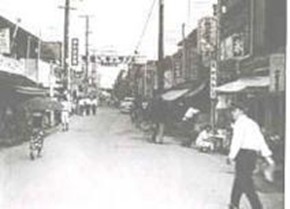
1896(明治29)年施行の郡制により、上妻下妻郡役所の管轄区域および生葉郡(現星野村の一部)の区域をもって八女郡が発足し、上妻郡は廃止されます。時は進み、第5回で紹介した八女遷都論を経て1951(昭和26)年、地域住民からの強い要望を受け、福島町、長峰村、三河村、八幡村、上妻村が合併し、福島町としての町域を拡大していきます。そして1954(昭和29)年、八女郡福島村に川崎村、忠見村、岡山村が編入し、八女市として市制が施行されました。
■八女市制化に向けて1954(昭和29)年4月1日に八女市は誕生しましたが、この際当時の住民たちのさまざまな思いや葛藤があったようです。
合併および市制化に伴い、市名を新しく定める必要がありました。そこで当時の福島町民たちは同年3月12日市名を「福島市」として提出します。そこには、「福島提灯」や「福島仏壇」など伝統を誇る地名の存続に強いこだわりが見られます。しかし県からは「福島県福島市とかぶる」という理由から許可が下りず、激しい運動が展開されました。次案の「筑後福島市」も隣の市に「筑後市」として発足するためこの案も却下されました。
町民側からは「新福島市」の案も出ましたが、周囲の同意を得られず、最終的に八女市に決まったのは新市発足の半月前でした。その後2006(平成18)年には上陽町が、2010(平成22)年には黒木町、立花町、矢部村、星野村が合併して現在の八女市の姿となりました。

現在福島の地名は消えていますが、伝統工芸品や八幡宮には今も福島の名は残り続けています。こうした当時の福島町民に思いをはせながら当館を含む八女市へ足を運んでみてはいかがでしょうか。
■次回予告次回は上妻下妻郡役所の歴史をつなぐ旧八女郡役所についてご紹介します。















-1-180x180.jpg)